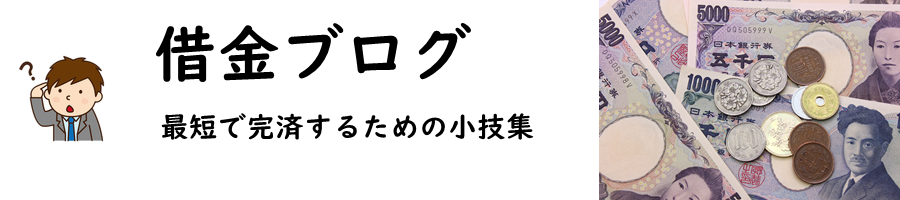
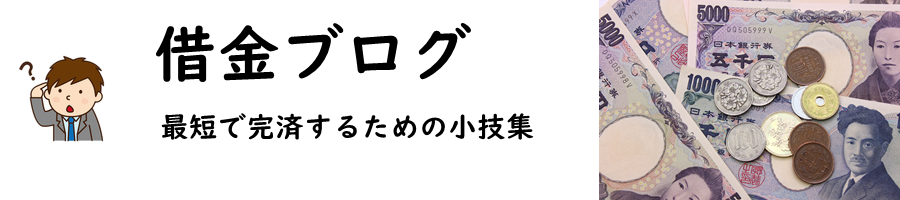
開発費の繰延資産処理と国税庁規定
開発費を一括費用処理すると税務否認される場合があります
開発費における繰延資産の定義と国税庁の見解
国税庁は開発費を「新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用」と定義しています。この定義は法人税法施行令第14条第1項第3号に規定されており、税務上の取扱いにおいて重要な基準となります。
参考)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
開発費が繰延資産として認められるのは、その効果が翌期以降に及ぶためです。具体的には支店開設のための広告宣伝費や接待費、新技術導入のための調査費用などが該当します。これらの支出は一時的に多額になりやすく、発生年度だけに費用計上すると財務状況が大きく変動してしまいます。
参考)繰延資産の開発費処理と研究開発費の違いについて - ゼロス有…
つまり繰延資産処理が認められるということですね。
ただし毎年定期的に支出される費用は、開発費として繰延資産に計上できません。これは経常的な費用と特別な支出を区別するための重要なルールです。国税庁の通達では、臨時に発生する費用のみを開発費として扱うよう明確に指示しています。
参考)[繰延資産の基本知識]対象項目や償却方法を押さえよう|経費精…
税務調査で問題になりやすいのは、この「特別に支出する費用」という要件です。どういうことでしょうか?
通常の営業活動に含まれる費用を開発費として処理してしまうと、税務否認のリスクがあります。例えば毎年実施している市場調査の費用を開発費として繰延資産計上すると、税務署から指摘される可能性が高くなります。
開発費の償却期間と国税庁が認める方法
開発費の法定償却期間は5年以内とされています。この期間内であれば、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却することが認められます。国税庁は特に償却方法を限定しておらず、企業の実情に合わせた処理が可能です。
参考)会計基準詳細
税務上の最大の特徴は、開発費が任意償却の対象になることです。支出した開発費のうち、法人が損金経理した金額が損金として認められます。これは創立費や開業費と同じ扱いであり、他の繰延資産とは異なる柔軟な処理が許されています。
参考)https://hyodo-ao.net/blog_hyodo/blog_hyodo_3/deductible-expense.html
任意償却が基本です。
具体的には利益が多い年度には償却額を増やして節税し、利益が少ない年度には償却額を抑えることができます。極端なケースでは支出した事業年度に全額即時償却することも可能です。この柔軟性は税務担当者にとって大きなメリットとなります。
参考)創立費と開業費などの繰延資産の任意償却~知っておきたい法人節…
未償却残高がある限り、いつでも償却費として必要経費に算入できます。制限期間がないため、5年を超えても償却を継続することができます。これは開発費の任意償却における独特の取扱いです。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/deferred-asset/
国税庁が認める開発費の償却方法
| 償却方法 | 特徴 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
|
均等償却(定額法) |
5年間で毎年均等に償却 | 一般的な方法として広く認められる |
| 任意償却 | 利益状況に応じて自由に設定 | 損金経理した金額が損金算入される |
| 即時償却 | 支出年度に全額償却 | 金額の大小に関わらず可能 |
開発費の繰延資産化における研究開発費との違い
開発費と研究開発費は名称が似ていますが、会計・税務上の取扱いが全く異なります。この違いを理解していないと、誤った会計処理につながる危険性があります。
参考)企業会計における開発費と研究開発費の違い
研究開発費は会計基準により発生時に全額費用処理することが義務付けられています。これは「研究開発費等に係る会計基準」で明確に規定されており、原則として一般管理費に計上します。繰延資産として計上することは認められません。
一括費用処理が原則です。
一方で開発費は財務諸表等規則第36条において繰延資産として認められています。支出時に費用処理することも可能ですが、効果が翌年以降に及ぶ場合には資産計上することができます。この選択肢があることが研究開発費との大きな違いです。
税務上も同様の区別があります。研究開発費に該当するものは原則として発生年度の損金となりますが、開発費として繰延資産計上したものは任意償却の対象となります。
実務では「研究開発費に含まれる開発費」という概念があり、一定条件のもとでは繰延資産として計上できます。具体的には支店開設などの市場開拓費用は研究開発費ではなく開発費として処理すべきケースです。
どういう場合に繰延資産にできるんでしょう?
効果が翌年以降に及ぶことが明確で、経常的ではない特別な支出であれば繰延資産化が可能です。例えば新市場への進出に伴う大規模なプロモーション費用などは開発費として資産計上できます。
研究開発費として処理した場合は発生した期に一括で費用計上されますが、開発費を繰延資産として資産計上した場合には効果が持続する期間において償却を行うため、費用が該当期間にわたって均質的に発生することになります。
国税庁通達に基づく開発費の具体的な処理例
国税庁の基本通達では開発費の具体例として、支店開設などのために支出した広告宣伝費や接待費を挙げています。これらは新たな市場の開拓という開発費の定義に該当するためです。
新技術の採用に関する費用も開発費となります。例えば製造ラインに新しい生産方式を導入する際の調査費用や、社員研修費用などが該当します。ただし製造設備そのものの取得費用は固定資産となり、開発費には含まれません。
資源の開発のために特別に支出する費用も繰延資産の開発費です。鉱山開発や原材料の新たな調達ルート開拓などが典型例となります。国税庁通達ではこれらを明確に区分しています。
参考)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm
開発費として処理できないケースもあります。
具体的には研究開発費として全額費用処理が義務付けられている支出です。新製品の試作費用や新規原理の発見のための研究は、税務上「試験研究費」に該当し、繰延資産としては認められません。
参考)http://www.asuna-accounting.com/info/research_ex01.html
実務での判断基準として、その支出が「研究」なのか「開発(市場開拓等)」なのかを明確に区分する必要があります。研究は具体的な成果につながる保証がないため繰延資産から除外されています。
毎年定期的に支出される費用は開発費として繰延資産に計上できません。これは経常的な費用と臨時の特別支出を区別するための重要なルールです。例えば毎年実施している広告宣伝費は、たとえ新規顧客開拓が目的でも開発費にはなりません。
開発費として繰延資産化できる支出とできない支出
| 繰延資産化できる開発費 | 繰延資産化できない支出 |
|---|---|
| 新市場開拓のための臨時的な広告宣伝費 | 毎年定期的に行う広告宣伝費 |
| 支店開設に伴う特別な接待費 | 通常の営業活動での接待費 |
| 新技術導入のための調査費用 | 新製品の試作費用(研究開発費) |
| 新規事業開始のための準備費用 | 具体的成果が不明な研究費 |
開発費の税務調整で注意すべき国税庁の指摘ポイント
開発費の税務処理で最も注意すべきは、会計上の処理と税務上の損金算入額の違いです。会計上は繰延資産として計上しても、税務上は損金経理した金額のみが損金となります。この差異を理解していないと、申告調整で誤りが生じます。
任意償却の特性により、開発費は会社が自由に償却額を決められます。しかし税務上の損金として認められるのは「損金経理した金額」に限定されるため、決算で費用計上していない金額を申告調整で損金算入することはできません。
損金経理が条件です。
会計上と税務上で開発費の範囲が異なるケースにも注意が必要です。会計上は研究開発費として一括費用処理すべきものを、誤って開発費として繰延資産計上してしまうと、税務調査で指摘される可能性があります。
国税庁は「特別に支出する費用」という要件を重視しています。経常的な費用を開発費として処理すると、税務否認のリスクが高まります。判断が難しい場合は、支出の性質や頻度を文書化しておくことが重要です。
開発費の効果が及ぶ期間についても慎重な検討が必要です。会計上は5年以内で償却しますが、実際の効果がそれより短期間で終了する場合には、合理的な償却期間を設定すべきです。過度に長期の償却は税務上問題視される可能性があります。
税務調査での立証責任は納税者側にあります。開発費として繰延資産計上する際には、以下の点を明確にしておく必要があります。
- その支出が新技術採用、市場開拓等の特別な支出であること
- 経常的な費用ではなく臨時的な支出であること
- 効果が翌期以降に及ぶと合理的に判断できること
- 研究開発費ではなく開発費に該当すること
これらの判断根拠を書面で残しておくと、税務調査時のトラブルを防げます。
償却方法の変更にも注意が必要です。任意償却を選択している場合、各期の償却額は会社が決定できますが、恣意的な利益操作と見なされないよう、合理的な説明ができる必要があります。
参考)繰延資産とは?対象項目や償却期間、活用方法を解説
厳しいところですね。
国税庁の通達や法令は定期的に改正されます。最新の情報は国税庁ウェブサイトで確認することが重要です。特に開発費の範囲や償却方法に関する解釈は、税制改正や新しい通達により変更される可能性があります。
国税庁の公式PDF「繰延資産の範囲について」では、開発費を含む繰延資産の定義と償却期間が詳しく解説されています
国税庁法人税基本通達「第1節 繰延資産の意義及び範囲等」では、開発費の税務上の取扱いと資源開発費用の具体的な判断基準が示されています


