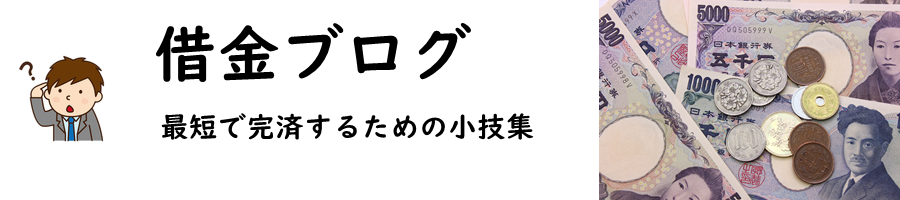
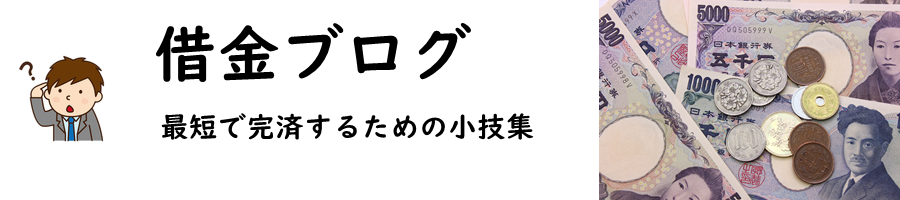
発注書 請求書 違い
発注書の役割と発行タイミングの違い
発注書は、商品やサービスを依頼する際に、発注者が受注者へ「この条件でお願いする」という意思表示をするための書類です。
実務では、受注者から見積書を受け取った後に、単価・納期・支払条件などを確定させて発行する流れが一般的です。
口頭やメールだけでも契約自体は進みますが、条件が記録として残りにくいので、認識違いによるトラブルを防ぐ目的で発注書を発行する価値があります。
経理目線のポイントは、「発注書=費用計上の根拠」ではない点です。
発注書は“依頼の証拠”として強い一方、実際に納品・検収が終わったか、請求額が確定したかは別管理なので、月次では次のように切り分けると混乱が減ります。
- 発注書:発注条件(単価、数量、納期、支払条件)が合意されたかの証跡
- 納品書・受領書:提供(納品)と受領(検収)の証跡
- 請求書:支払依頼(請求額確定)の証跡
請求書の役割と発行タイミングの違い
請求書は、商品やサービスの代金を「いくら・いつまでに・どこへ」支払うかを伝える、支払依頼の書類です。
取引フロー上は、納品や受領(検収)など取引が進んだ後に発行される位置づけで、発注書と同じ“帳票”でも目的がまったく異なります。
また、納品と受領が同時に行われるケースでは「納品書兼請求書」として提出される場合があるため、書類名ではなく中身(請求の意思・支払条件)で判断するのが重要です。
経理処理での実務的な違いは、「請求書が来た=即支払」ではなく、社内ルール(検収完了、稟議、支払依頼)を満たしているかの確認が必要な点です。
特に、発注書の段階で条件が固まっていても、納品数量の差異、追加作業、値引、返品などで請求額が変わることがあるため、請求書は“最終金額の提示”として別立てで確認します。
発注書と請求書の違いを取引フローで整理(見積書・納品書・受領書)
書類の違いは、単体で暗記するより「どの順番で出てくるか」を押さえるほうが実務では早いです。
代表的な流れは、見積書→発注書(注文書)→注文請書→納品書→受領書→請求書→領収書で、発注書と請求書はフロー上の位置が大きく離れています。
この順番で見ると、発注書は“開始の合意”、請求書は“完了後の支払依頼”という役割の差が自然に理解できます。
経理でありがちなミスは、「見積書の金額=請求書の金額」と決め打ちしてしまうことです。
見積書は条件提示、発注書は条件合意、納品書・受領書は履行、請求書は請求確定という意味の違いがあるので、照合は次の順で行うと堅くなります。
- 発注書 ↔ 見積書:単価、数量、納期、支払条件、値引条件
- 納品書 ↔ 発注書:数量、品目、納品日、分納の有無
- 請求書 ↔ 納品書・受領書:請求対象期間、差額(追加・返品)、消費税、支払期日
発注書と請求書の違い:記載項目と保存・送付の注意点
発注書には、宛先、発注番号と発注日、件名、発行元情報、納期・支払条件・有効期限、小計・消費税・合計、明細(単価・数量)などを記載するのが基本です。
また、発注書は税法上一定期間の保管が求められ、個人事業主は原則5年、法人は原則7年という整理で説明されることが多いです。
送付方法は郵送・メール・FAXがあり、取引先の指定がなければコストとスピード面からメール送付が勧められるケースがあります。
ここで、意外と見落とされやすいのが「発注番号(管理番号)の設計」です。
発注書と請求書の違いを理解していても、番号がバラバラだと照合に時間が溶けます。実務では、次のような“照合しやすい設計”が効きます。
- 発注番号を、見積番号・案件番号と連動させる(検索性が上がる)
- 分納が多い取引は、発注番号+枝番で納品書・受領書を管理する
- 請求書に「発注番号」または「注文番号」を記載してもらう(照合作業の短縮)
さらに、下請法の対象になる取引では、発注書などの書面交付が義務になるケースがあるため、取引類型や相手先属性によって“必須書類”の扱いが変わる点も押さえておくと安全です。
発注書の法令対応(下請法の3条書面の要点がまとまっている)。
発注書の発行義務・下請法の記載事項(3条書面の12項目)を確認できる
発注書と請求書の違い:経理の独自視点(検収・内部統制・トラブル予防)
取引書類は「作る順番」だけでなく、「社内で誰がどこで止めるか(統制ポイント)」を設計すると、ミスが減るだけでなく不正リスクも下がります。
たとえば、発注書は現場(購買・部門)が発行し、請求書は経理が受領することが多いため、情報の非対称が起きやすい構造です。
この“ズレ”を前提にすると、発注書と請求書の違いは単なる帳票知識ではなく、業務設計のテーマになります。
実務で効くチェック観点は次のとおりです。
- ✅ 発注書:支払条件(締め日・支払日)、納期、単価、値引条件、上限金額(超過時の扱い)を明文化する(後出し請求の抑止)
- ✅ 納品書・受領書:検収日(受領日)を確定させる(計上月・支払サイトの基準になる)
- ✅ 請求書:請求対象期間、相殺(返品・値引)、振込先、支払期日を確認する(振込事故の予防)
「検収」があいまいだと、発注書の条件通りに納品されたのか、請求書の金額が妥当かの判定が遅れます。
その結果、締め後に差額が発覚して修正仕訳が増えたり、支払遅延(取引先トラブル)につながったりします。
発注書と請求書の違いを理解したうえで、検収の記録(受領書や検収印、受領日)を“支払可否のスイッチ”にする運用は、検索上位記事でもあまり正面から語られにくいですが、経理の現場では効き目が大きい論点です。


